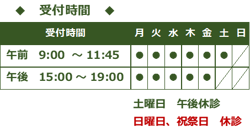アスレチック・トレーナー活動
当院は、多様なスポーツ障害に対して医療の視点からのみならず、予防の視点を重視した対応を通して、人々の健康増進に積極的に貢献するアスレチック・トレーナー活動をライフワークとし、推進しております。
|
アスレチックトレーナーは様々なスポーツシーンにおいて、より良いスポーツ環境づくりを追求し、様々な面からアプローチしていくことが使命です。 チームで活動する場合には、選手のコンディショニング指導からケガの応急処置、ケガからの復帰までのリハビリテーションが最速で終了するためのプランニングと指導、監督やコーチとの連携による円滑なチーム運営等、実に様々な要素からの環境づくりを行います。 |
|
アスレチックトレーナーの認知度は徐々に上がってはおりますが、まだ十分に社会に浸透しているとは言いがたいのが現状です。 少しずつでも活動している我々が認知度を向上させるような働きかけを行い、少しでも早く周知の職業として確立されることを願っております |
| ★ アスレチックトレーナーの仕事 |
| 1. 選手の健康管理 | |||
| ① 応急処置 | |||
|
選手がケガをした際には損傷の程度を迅速に確認し、その後に対処方法の判断を行います。 程度によっては医療機関への搬送が優先される場合もあり、医師がいない場合のトレーナーの判断は重要になります。 |
|||
| ② リハビリテーション | |||
|
ケガからのスポーツ復帰を目的とするリハビリテーションではトレーナーの役割は重要となります。 医師との相談に基づいて、最短の復帰プログラム作成と指導を行います。 |
|||
| ③ コンディショニング指導 | |||
|
ケガの有無に関わらず、ケガをしないようにコンディショニング指導することも重要な役割です。 コンディショニング調整は、自己管理できるように選手に自覚させ、自己管理できるように導いていきます。 |
|||
| ④ 記録 | |||
|
各選手の既往歴やコンディショニングを記録し、今後の活動にフィードバックしていきます。 また、監督やコーチとの情報共有のために選手のレポートを作成したり、診察が必要になった際には医師への申し送り書を作成したりする場合もあります。 |
|||
| 2. トレーニング指導 | |||
|
① |
各選手によって得意な能力とそうでない能力があり、さらに競技によって必要とされる能力は異なります。 そのため、アスレティックトレーナーは競技特性を分析し、実施競技において求められる能力を把握します。 | ||
|
② |
次に選手の身体的能力を把握するのに体力測定を実施し、必要な能力と現在の能力を数値化します。 | ||
|
③ |
目標が明確になったら、競技力を向上させるトレーニングメニューを作成し、実際に指導していきます。 | ||
|
④ |
併せて、競技のシーズンを考慮し、パフォーマンスのピークをどの時期に合わせるかという判断も必要になります。 | ||
| 3. 選手の教育とカウンセリング | |||
|
若い年代のチームの場合には、スポーツを通じて教育的指導を行います。 また、選手の中には様々な悩みを抱えていることがあり、心理的なケアを行うことも大切な役割となります。 |
|||
| 4. こんなことも・・・・ グランドやトレーニングルームの管理 | |||
|
選手が競技やトレーニングを行うにあたって、アスレティックトレーナーは安全管理に努めます。 グランドやトレーニングルームの危険因子を確認し、効率的な環境づくりを行います。 |
|||
| ★ アスレチックトレーナーに必要な知識とは | |
|
アスレチックトレーナーとして活動するには、医学的な知識が必要不可欠になります。 養成校では、解剖学、内科学、運動生理学、バイオメカニクス、心理学、栄養学等の体に関する内容の教科が並びます。 さらにスポーツ選手を対象とするトレーナーはスポーツ医学が必要となり、基礎医学と共に臨床医学まで学習が必要となります。 実習として学ぶ内容としては、アスレティックリハビリテーション、テーピング法、トレーニング法、ストレッチング、救急法などがあり、知識と同時に臨床の経験も重要となります。 |
|
|
このように仕事の対象が選手(人の身体)であり、医療従事者と同様に重大な責任が伴います。 軽率な行動や知識不足は、選手の身体を傷つけかねないというリスクを含んでいます。 リスクを回避するためにも我々アスレチックトレーナーは、常に知識の代謝を心がけております。 |
|
| ★ スポーツに深く関わるために欠かせない資格 | |
|
日本国内においてスポーツトレーナーの資格は民間資格しかありません。 ・ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の「認定アスレチックトレーナー」 |
|
|
実はこの資格だけではアスリートの体に触れることはできません。 マッサージなどの施術をするには、柔道整復師や理学療法士などの医療系国家資格が必要で、現在活躍しているほとんどのスポーツトレーナーは、この国家資格も併せて取得しています。 |
|
|
院長は、ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会 「認定アスレチック・トレーナー:JATAC-ATC」です。 |
| 主なアスレチックトレーナー活動 |


|
・実業団宮田自動車バスケットボール部 トレーナー (平成12年~平成22年) |
| 全日本総合バスケットボール選手権大会8回帯同 |
| 国体バスケットボール成年男子6回帯同 |
| 全日本実業団バスケットボール選手権大会2回帯同 |
| 全日本実業団バスケットボール競技大会1回帯同 |

|
・全日本中学通信陸上競技 北海道札幌大会4回 (救護、コンディショニング) |

|
・社会人400H及び110H 個人選手 (コンディション契約) |